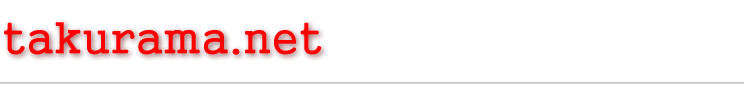 |
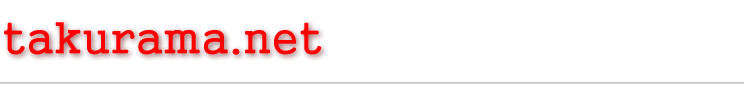 |
| トップ > コラムと旅行記 > 「火星のわが家」の主(あるじ)を送る |
 「火星のわが家」の主(あるじ)を送る 「火星のわが家」の主(あるじ)を送る〜木口和夫さんのこと〜 今年(2007年)が始まって間もない1月6日朝、1通のメールが届いた。差出人は劇作家の若林一郎さんで、「昨夜木口和夫君が亡くなりました」とのごく短い文面。かねてから病気療養中で、週に3回人工透析を受けていたことは知っていたが、昨年秋まではほぼ毎月「風の便り」という身辺雑記を送ってきてくれていたから、あまりのあっけなさに、ただ呆然とした。享年79歳。 木口さんとの付き合いは古い。私の父・青江舜二郎が鎌倉アカデミアという、戦後4年半しか続かなかった幻の大学で演劇の講義を担当していた時の教え子である。先ほど名前の出た若林さんや、以前「カナカナ」という映画に出てもらった川久保潔さんや岩崎智江さんもそこのご出身。学校そのものは短い命だったが、閉校後も父と教え子諸氏との交遊は続き、特に木口さんは奥様もアカデミアのご出身ということもあり、家族ぐるみでお付き合いのあった数少ない人であった。若い時には早川書房の編集部に勤め、戯曲を発表したりもしていたらしいが、結婚を機に、食肉を扱う事業に身を転じ、私がものごころついた時分には、経営者として大変忙しく働いておられた。しかし創作への志は失わなかったようで、いつまでも父を「青江先生、青江先生」と慕い、よくわが家を訪ねてきてくれた。長野県黒姫の山荘に、奥様、ふたりのお嬢様とともに遊びにいらしたこともある(それは私が小学校6年生の夏のことであり、そろって野尻湖畔の遊泳場に泳ぎに行ったのだが、当時まだティーンエイジだったお嬢様たちの水着姿が、たいへんまぶしかったことが思い出される)。 これは木口さんを知る誰もがおっしゃることのようだが、彼は大変に面倒見のよい性格で、困っている人には手を差し伸べずにはおられない、いわゆる善意の人であった。私の父は、私が中学1年だった1976年の秋に脳梗塞で倒れ、長い療養生活に入るが、それ以降、芥川龍之介の「杜子春」に出てくるような、世間の「掌を返したような仕打ち」というものをずいぶん見て来た。「現役を退いた者に付き合っているヒマはない」という現世利益的な人間があきれるほど多く、ああ、これが世の中というものか、と、落胆することがしばしばあったが、そんな中で木口さんだけは、父が倒れるまでと変わらず、いやむしろ、病気で何かと不便があるのでは、と、以前にもましてまめまめしくわが家に足を向け、病院への送迎など、いろいろと手助けをしてくれた。彼だって働き盛りの忙しいさなかである。なかなかできることではない。「今度お見舞いにあがります」などと口で言うのはたやすいが、実行するのは面倒なものである。それだけに木口さんの誠意は心に沁みた。 1983年に父が亡くなった時、真っ先に病院に駆けつけてくれたのも木口さんと若林さんで、葬儀の時は、お二人が鎌倉アカデミアの卒業生代表として式全体を仕切って下さった。1985年の三回忌に「引っ越し魔の調書」という随想集を出した時は、校正や発送作業を手伝ってくれているし、同じころに私が大学のサークルで自主映画を作った時にも、伊東のリゾートマンションや鶴見でやっていたお店をお借りしている。その後も家ぐるみでのお付き合いは続き……、というより、代が変わっても、お世話になることはあい変わらずで、どうも作家とか監督という人種は、相手が甘えられる人だとわかっていると、とことんまで甘えてしまう悪い癖があるようだ。その辺の記憶をたどれば話は尽きないが、中でも、私にとってとりわけ思い出深いのは、1998年に「火星のわが家」という映画を撮った時に、木口さんの横浜の御宅を、作品の舞台としてお借りしたことだろう。この映画をご覧になった方はわかると思うが、日下武史さん演じる神山康平という「火星博士」が住んでいた、まるで宇宙船のような丸窓が印象的な家である。  撮影当時の木口邸(1998年) 撮影当時の木口邸(1998年)あの当時、「築年は経っているけれど洒落ていて知的な雰囲気の家」という台本のイメージに合う一軒家がなかなか見つからず難渋していたのだが、ふと、「木口さんの御宅は渡辺優さんというデザイナーが設計を手がけた、なかなかモダンな家だったはずだ」と思いつき、早速お家をお訪ねして交渉してみたところ、「二年後には取り壊して二世帯住宅に立て替える予定だから、どうぞご遠慮なく」と、その場で承諾をいただいた。さすがに困っている人は助けたくなる性分だけのことはある。しかし、ふたつ返事で家を貸すことを了承したはいいが、実際に生活している御宅に、15人近い撮影隊が連日押しかけたのだから、木口さんもたまったものではなかったろう。それも2日や3日ではない。たっぷり2週間である。初めのうちは、1階の居間を撮影している時には2階に、2階の書斎を撮影している時には1階に、という具合に部屋を移動しながら生活されていたのだが、自分の家なのにおちおち昼寝もできないという悲惨な状況に耐えかね、しまいには奥様とお孫さんたちを連れて、伊東のマンションまで緊急避難した、なんていう笑えないエピソードもある。まさに「軒先を貸して母屋を取られた」わけだ。今思い出しても恐縮しきりで、この件だけでも、木口さんには足を向けて眠れない。しかし、あのお家を使わせてもらえたことで、作品に独特の奥行きとリアリティが出たのはまぎれもない事実で、「どんなに高価なセットを組んでも、これだけの生活の重みは出ませんね」と、芦澤明子カメラマンも、大変お気に入りのご様子だった。作品を見てくれた方の感想をネットなどで拝見しても、「作品は今イチだったが、あの家は必見だ」なんていうものさえある(こういう感想は素直には喜べないが……)。  「火星のわが家」の製作裏話はこちらをどうぞ 「火星のわが家」の製作裏話はこちらをどうぞなおもうひとつ、この話には意外なサイドストーリーがある。世間は狭いというべきか、この家の主人役をやった日下武史さんの奥さんが、何と鎌倉アカデミアの演劇科で木口さんの一級後輩だったのである。私はもちろん、そんなことは全然知らずに日下さんに出演を依頼したのだが、撮影初日に木口さんが日下さんに、「実はそちらの奥様と私とは…」と、先輩後輩であることを打ち明け、日下さんもその意外なつながりに、ただでさえ大きな目をさらに丸くしたのであった。その後、病気療養中という日下さんの奥様から木口さんに、「まるでタイムスリップしたような、懐かしい偶然です」というお手紙が届いたそうである。
そして、撮影から1年半が経った2000年の1月。「火星のわが家」公開を1ヶ月後に控え、木口邸は予定どおり取り壊されることになり、その直前に私は思い出多き「わが家」を訪ね、別れを惜しんだ。撮影で2週間通っただけなのに、やはり自分の作品の舞台となった場所というと思い入れも強く、「まだまだ使えるのに、もったいないですよねえ」と、変に感傷的になったものである。しかし、当の木口さんは、「いやあ、もうずいぶん痛んでいるから」と、案外サバサバしているように見えた。他人にはあれだけの思いやり、心配りを見せる人が、自分の慣れ親しんだ家に対してはずいぶんあっさりしているなあ、と少し不思議に思ったものである。半年後には新居も完成したとのことだったが、そちらにおうかがいするチャンスは得られないまま時が流れ、木口さんがご存命中にお宅を訪ねたのは、この時が最後になってしまった。したがって、木口さんとあの家とは、今でも私の記憶の「止まった時間」の中に、仲良くワンセットでいるのである。 その後はお会いする機会も減っていったが、ほぼ毎月書いておられる「風の便り」で近況はおおむね把握することができた。一昨年、父の生誕百年記念のCD「水のほとり」とDVD「実験室」の2本を出した時も、かなり好意的な感想を寄せていただいているし、昨年5月に、鎌倉アカデミア創立60周年イベントが材木座の光明寺で開かれた折にもご出席されている(本堂で記録のビデオカメラを回していた私はあいにくお目にかかることができなかったが)。だから、ご病気とは言っても、うまくその病気と共存されているように感じていた。ただ、9月の「風の便り」の巻末に、「しばらく執筆をお休みします」との一文があり、それが気になって、「一度是非お見舞いに…」と打診をしたのだが、「遠方から来ていただくのも申し訳ないので」と奥様経由でご辞退の返事をいただいた。そして4ヵ月後の今年1月6日、冒頭の訃報が届いたのである。父の見舞いにあれほど何度も通ってくれた人を、ついに自分は一度も見舞うことができなかった…。悲しいというよりも無念さが先に立ったが、木口さんは、あれほどの人情家でありながら、人から情けをかけられることはあまり良しとしなかったようだ(人間の性質というのはそういうものなのかも知れない)。 告別式は1月12日、天王町の保土ヶ谷奉斎殿で行なわれた。ご遺体とも対面させていただいたが、何か、見てはいけないものを見てしまった気がして、どうにも心穏やかでなかった。今から二十数年前の父の葬儀の時、私は二十歳になったばかりで、身内の不幸はそれが最初であった。当然礼服も何も持っておらず、そんな私に、とり急ぎこれを、と、黒のネクタイと数珠を手渡してくれたのも彼であった。父の亡骸のすぐそばに座り、焼香の仕方から何から教えてくれ、葬儀の一切を仕切り、香典の計算や会葬者の名簿作りまで引き受けてくれたその同じ人が、今は斎場の真ん中で花に囲まれ、物も言わずひっそりと横たわっている。諸行無常である。人間というのは、送っていた側がいつか送られる側に回り、そうやって人の世は静かに続いていくのだなあと思いながら、彼からもらった数珠を手にかけ、静かに合掌したのであった。 それからさらに4ヶ月後の去る5月21日、鶴見駅ビルのとある店で「城井友治さんを偲ぶ会」が開かれた。城井友治というのは木口さんのペンネームであり、食肉関係の仕事を退いてからの彼は、その名前で「床あげ屋異聞」「芹沢鴨の生涯―新選組異聞」といった何冊かの本を世に出している。 会はなかなかに盛況で、呼びかけ人の若林一郎さん、小幡欣治さんを初めとする鎌倉アカデミア卒業生、文学横浜の会の同人の方がたなど五十人近くが集まった。たまたま座った席の向かいが、あの木口邸を設計した渡辺優さんだったというのも嬉しい偶然で、初めてお会いする渡辺さんから、いろいろと建築の裏話をうかがうことができた。家のことでいえば、木口さんのお嬢様からも、 「父はあの映画を撮っていただいたおかげで、わが家がいつまでも残ったことをとても喜んでいました。NHKのBSで放送された時もとても嬉しそうで…」 とお礼を言われ、さんざんお世話になった恩返しが、少しはできたのかも知れないと、心がほのぼのするのを感じた。 他にも、短い時間ながら、思いがけない方たちとの出会いがあり、「ああ、亡くなったあとも、木口さんはこうしていろいろな人と人とをつなぐ世話役をやられているのだなあ」と、しみじみ感じたのであった。と同時に、この楽しくなごやかな宴席に、主役であるはずの木口さんがいないのはどうしたことだろう、と、改めて「偲ぶ会」というものの不条理さを思ったのもまた事実である。父の代から何十年という付き合いがあり、手をのばせば、いつも届くくらいに思っていた近しい人が、今では会場の壁際に、花とともに飾られた一枚の写真になっている…。しかし、いたずらに感傷にふけるほど人生は永くない。自分もまた、いずれはあちらに行く身なのである。最後まで月並みな言葉しか出てこない、おのれの表現力の貧しさにはほとほと悲しくなるが、お別れの言葉はただ、ひとこと。「木口さん、今まで本当にどうもありがとう!」 (2007/06/01) |
トップ|プロフィール|作品紹介|コラムと旅行記|ブログ|タイムスリップタクラマ|フォトギャラリー|アーカイブ (C)OSHIMA TAKU All Rights Reserved. |