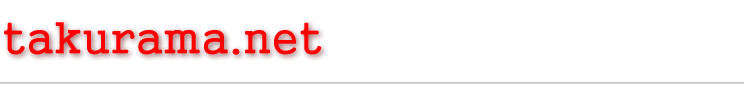 |
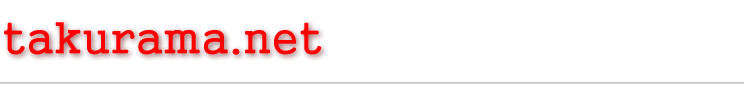 |
| トップ > コラムと旅行記 > 三日見ぬ間の… |
 三日見ぬ間の… 三日見ぬ間の…今いる部屋の窓からは、隣家の立派な桜が見える。数日前の暖かさで一気に開花し、ほぼ満開状態だ。 毎年この季節になると思うのだが、どうして桜が咲く頃にはひどい雨が降ったり、強風が吹いたりして、せっかくの花をこれでもかというほど苛むのだろう。もともと、咲いたと思えばぱっと散る、はかなさの代表格みたいな花なのだから、その間くらいはそっとしておいてやればいいのに。それにしても「三日見ぬ間の桜」とはよく言ったものだ。窓のすぐ外なので毎朝観察していたのだが、前の日までは硬いつぼみだったものが、翌朝にはすっかり花びらを開いてしまうその素早さには、こちらまで目を見開かされた。以下はその様子を記録したものである。  3/27 まだほとんどがつぼみ 3/27 まだほとんどがつぼみ 3/29 そろそろ下の方から… 3/29 そろそろ下の方から… 3/30 前の日の暖かさで一気に! 3/30 前の日の暖かさで一気に! 3/31 曇天でも勢いは止まらない 3/31 曇天でも勢いは止まらない 4/1 新年度とともに満開!! 4/1 新年度とともに満開!!桜といえば季節の変わり目に咲く花の代表格で、卒業や入学、転勤など、新たな旅立ちに彩りを添えるといった印象が強いが、その一方、梶井基次郎の「桜の樹の下には」や坂口安吾の「桜の森の満開の下」といった小説もあるように、その美しさの裏に不穏な死の影を感じさせる花でもある(まあ死も「旅立ち」には違いないが)。自分の体験を顧みても、父が亡くなったのが4月の末で、当時入院していた病室の窓から大層見事な桜が見えたのが、強烈なビジュアルイメージとなって鮮明に残っている。今でも桜をながめる時、「ああ、きれいだなあ」という気持ちとともに、どこかやり切れない、心の奥を爪で引っ掻かれるような感覚を味わうのはそのせいだろう。そして、それはおそらくこれからも、春が来て桜が咲くたび、胸の中で再現されるに違いない。しかし、現実に目を移せば、その病院も昨年閉院となり、もはやあの桜をながめながら黄泉(よみ)の国に旅立っていく病人もいなくなった。桜は三日でその姿を変えるが、われわれを取り巻く環境も、われわれ自身もまた、あわただしく変わっているのだ。そういえば冒頭の言葉はもともと、 世の中は 三日見ぬ間の 桜かな という大島蓼太の俳句から来ており、「三日見ないうちに散ってしまう桜のように、世の中もまた移り変わりが激しいこと」を詠んだものであった。 たしかに時は気ぜわしく過ぎ、何も確かなものを手元に残していかないように思える。しかし、自分が桜をながめる時に湧き上がる複雑な感情は、あの病院の窓越しの風景とともに、これからも記憶にとどまり続けるのだろう。つまるところ「変わらずにあり続けるもの」などというのは、人間の心の中にしか存在しないのかも知れない。そんなほろ苦い気分を、つかのま呼び起こしながら、あと数日で今年の桜も散り去っていく。 (2007/04/01) |
トップ|プロフィール|作品紹介|コラムと旅行記|ブログ|タイムスリップタクラマ|フォトギャラリー|アーカイブ (C)OSHIMA TAKU All Rights Reserved. |