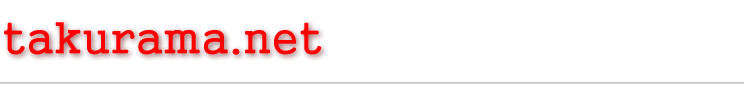 |
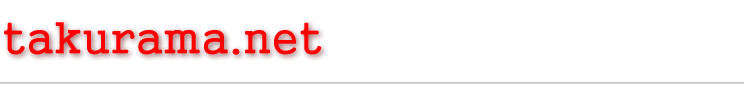 |
| トップ > コラムと旅行記 > 冬と春の間で |
 冬と春の間で (4月) 冬と春の間で (4月)いよいよ新年度。とはいえ、ここ数日は到底春だとは思えないような寒さ。まるで真冬に戻ったみたいだ。「花冷え」にしては厳しすぎるのでは? などと身を縮めつつ、去る3月27日、まだ雪がこんもり残る新潟・妙高高原に行ってきた。 といってもプライベートではない。この冬発売になったばかりのP社のデジタルビデオカメラの試し撮りのためである。やや専門的な話になるが、この新型カメラは2つの点で画期的だと言われている。まず、すでに劇場用作品にも多数使われているHD(ハイビジョン)カメラのハンディ版であること。そして、映像の記録メディアが従来のテープではなく、P2カードであるということ。これまではビデオ作品といえばテープ収録が当たり前だったが、今回の機種は、デジカメと同じ、メモリーカードにすべての情報を記録するのである。したがって、撮影した画像もデジカメのようにインデックス表示で呼び出せ、再生もワンタッチ。これは、その場で撮影された映像を確認したい場合などかなり便利なはずである。しかし、収録時間がカード1枚につき約8分(HD収録時)とテープに比べてかなり短いなどの問題もある。さて、実際の使い勝手はどんなものだろう。 というわけで、これまでもさんざんいろんな作品でお世話になってきたカメラマンの三本木久城さん、そしてカメラの手配をしてくれたプロデューサーの露木栄司氏と3人、朝の7時半に池袋に集合し、関越&上信越道を通ってはるばる妙高まで行ってきた。そもそも新しいビデオカメラの試し撮りになぜわざわざ雪国まで? と不思議に思われるかも知れないが、ビデオカメラは暗い被写体には強い反面、白くて明るめの被写体が苦手で、露出をあけ気味にするとすぐ画面が白くすっ飛んでしまう。それはフィルムで撮っても同じなのだが、フィルムの白飛びはそれなりに味があるのに対し、ビデオの白はただ「のっぺり」して鑑賞に堪えない場合が多い。したがって、白飛びがおきないギリギリの露出を設定する必要がある。ある意味で、晴れの日の雪景色というのは、そのカメラの画質の精度を試す格好の「悪条件」なのである(かなり前置きが長くなってしまいました。あと、この手の文章を書くとどうしても技術用語が多くなって申し訳ないです。カメラについての詳細は、三本木さんが4月号の「ビデオα」にテストレポートを掲載しているので是非そちらをお読み下さい)。   午前11時、現地に到着。すみやかに雪のある場所でのテスト撮影を行なったのだが、予想に反してカメラの表現力は優秀で、やや露出オーバー気味の画面でも、それほど無惨な白飛びは起きなかった。日なたから日陰に人物が移動するショットを手持ちカメラで追う、というのを露出を変えつつやってみたが、これもかなりスムーズで、思った以上にオーバーとアンダーの許容範囲が広いというのがよくわかった。さすがはハイビジョンである。現場にはモニターを持っていかなかったので、撮影後、三本木さんの映画仲間で長野市在住の檜山さん宅にお邪魔し、かなり大型のハイビジョンモニターで映像をひととおり再生してみたのだが、「このコンパクトなカメラでこれだけの画が撮れるのか」と、思わずため息がこぼれた。また、気になっていたP2カードの収録時間だが、今回は試し撮りということもあって、持っていった2枚のカードで間に合った。午前の予定が終わったあと、昼食を取った食堂で収録データをノートPCに移してもらったが、これもスムーズに(ほぼ実時間で)終了。こうやってこまめにデータを移し替えてカードを空にしておけば問題はないというわけである。何より、すぐに画面のチェックができるのが便利でいい。しかもテープの場合、再生を繰り返すとテープが磨耗しノイズの原因になる恐れが常にあり、そのため現場での再生をためらってきたカメラマンが少なからずいると思うが(私も自分がカメラマンを兼任した時はそれがいつも不安の種で、あまりひんぱんに再生しないように心がけていた)、P2カード収録の場合はすべてがデータなので、ノイズが入る心配もない。心安らかにプレイバックできるというわけである。いやはや、まさにいいことずくめではないか。  食事中、データをノートPCに移す 食事中、データをノートPCに移す 左から露木、三本木、大嶋 左から露木、三本木、大嶋と、ここで文章を終わらせておけばメーカーさんも大喜びなのだろうが、すべて物事には功罪の両面がある。獲得したものと同じくらい多くのものを、われわれは必ず失っていると知るべきである。デジタル技術の進歩も例外ではない。手軽に高画質、手軽に再生、大いに結構。しかし、何か大切なことが忘れられていると、檜山宅のクリアなモニター画面を見ながら感じたのであった。それは、20世紀の「映画」が、フィルムという完全には制御できないマテリアルから生み出されたという事実である。ここ10年のデジタル技術の普及で、今や「フィルムで撮らなければ映画ではない」などと大真面目に言う人もほとんどいなくなった(ように見える)が、フィルムとビデオには、やはり決定的な違いがある。それは単に「画質」の問題ではなく、「本質」に関わる相違といっていい。 私が初めて体験した「映画」は8ミリフィルムであった。それは、光に透かすと人物が、風景が、厳然として映っている「実存」であった。その、実際に画が写っている、この世でただひとつしかないフィルムをスプライサーで切る時の不安と歓喜。「切り間違えたらどうしよう?」息を殺して、スプライサーにフィルムを装填する、それは神聖な儀式であり、その時の手の感覚は、今も生々しく覚えている。また、映写機を通したフィルムが、不意のトラブルで詰まりを起こし、それが燃えてしまった悲しい記憶は、8ミリ体験者なら誰でもお持ちだろう。「実存」していたものが、無惨に焼けただれて、2度と元には戻らない。何と言う喪失と悲哀! 自分は何度も、失われた「かけがえのない」映像のために涙した。 それが、次第に時代はビデオテープに取って替わられる。ビデオに記録されるのは「信号」であり、ビデオテープを透かしてみても、何も写ってはいない。編集も、信号を移し変えるだけのものになり、切り間違うとか、焼けるとかの心配もなくなった。しかしテープを使う限り、テープそのものが切れるとかからまるといった、一応は生々しいトラブルも起こり得た。それが今度は、テープさえ必要のない時代の到来だ。ついに映像は0と1という2つの数字の集積となり、作り手の完全な管理下におかれていく。「実存」から「信号」へ、そして「データ」へ。われわれの生活がパソコンや携帯の普及で、日増しに「動物」としての生々しさを失っていくように、作り出される映像も、どこか生命力の希薄なものになっていくような気がする。それを映像表現の進化と呼んで素直に喜んでいいのだろうか。 ロサンゼルス在住のカメラマン・宮野宏樹氏は昨今の現状を分析し、こう語ってくれた。 「芸術と呼ばれるものには、ある種のブラックボックスというか、人智のおよばない、神がかりの部分が必ず存在する。例えば、焼き物がどういう具合に焼きあがるかは、その時の窯の温度や土のこね方といった、ある種偶然的な要素に左右される。映画も、かつては『現像』というブラックボックスを経由していた。撮影した画面が、どう仕上がってくるか、現像所に行ってラッシュを見るまでわからない期待と不安。その不確定性が、映画を映画たらしめていたように思う。ミステリアスな要素のなくなった今の映画は、芸術(アート)ではなく技術(テクノロジー)なのではないか…」 私はこれを名言と受け取り、激しく同意した(2ちゃんねる風に言えば「禿同」)。しかし、古いシステムを持ち上げ、新しいシステムに苦言を呈するのは、時代に着いて行けなくなったシニアのお決まりの態度であり、それは懐かしさ半分の愚痴と言えなくもない。時代は後戻りできないのだ。 そしてまた、ある作品がフィルムで撮影されたか、あるいはビデオで撮影されたか、それは、ほぼ100パーセント作り手側の問題であり、受け手(観客)にはさほど重要ではないのかも知れない。プロデューサーの露木氏は、私のそんな逡巡を見透かしたかのように言い放った。 「大切なのは、何で(どういうカメラで)撮るか、ではなく、何を(どういう作品を)撮るか、でしょう」 これもまた名言である。まさに「人の数だけ名言がある」だ(←これも名言?)。かくして、「実存」と「データ」とは私の中で激しく火花を散らせ、それはまるで、最近の冬と春のせめぎあいのように今も続いているのである。 (2006/03/31) |
トップ|プロフィール|作品紹介|コラムと旅行記|ブログ|タイムスリップタクラマ|フォトギャラリー|アーカイブ (C)OSHIMA TAKU All Rights Reserved. |